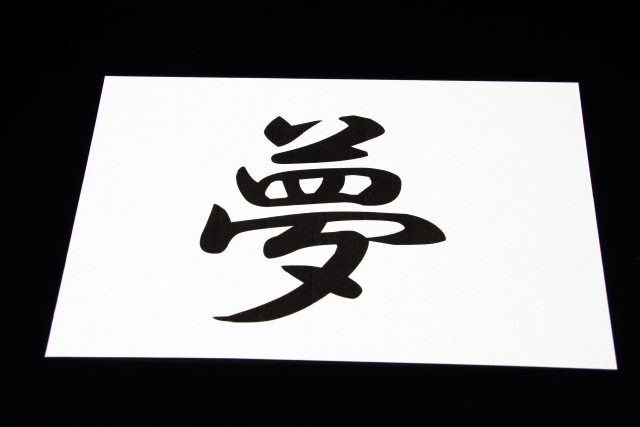小正月の由来・意味は何?どんな食べ物を食べるの?

1月には日本らしい様々な行事がありますね。
その1つが小正月です。
でも、小正月のことって、あまりよく知らないことの方が多いのではないでしょうか。
では、小正月とはどういうものなのか、よくある疑問点から3つにまとめてみましたので、参考にしてみて下さいね。
[ad-kiji-1]
小正月の由来・意味は何?
まずは、小正月の由来や意味からお話ししましょう。
古来の日本では、太陽や月の満ち欠けを基にした太陰太陽暦で日にちをみていました。
簡単にいうと、満月から次の満月を1ヵ月と数えていました。
人々は、何か新しいことやお祝い事をするならば、満月の時にという考えがあり、その年になって最初の満月の時を小正月として行事をするようになりました。
本来の正月である1月1日は、神様をお迎えし新年を祝う日として大正月、小正月は人々が新年を迎えてお祝いするという考え方もあったようです。
小正月はいつ?
カレンダー上では、1月15日が小正月にあたります。
つまり、旧暦ではこの日が年初めの満月で、正月だったわけです。
ただ、何度も書きますが、小正月の考え方は今でも地域による違いがあり、満月の15日をはさんで14日から16日を小正月としているところもあれば、14日日没から15日日没までとするところ、また1日から15日までを小正月とするところもあります。
ですので、小正月の行事をするならば、地域の考え方に合わせて行うのも良いのではと思うので、調べたり聞いたりしてはどうでしょうか。
小正月にやる行事って何?
1月1日は神様を迎える大正月なのに対し、15日は庶民の正月であると書きました。
正月行事には、その一年の世の中の吉凶を見る物が多くありますが、庶民の正月である小正月には庶民の生活に直結する行事がいくつかあります。
まずはよく知られているどんど焼きです。
これは、神様をお迎えするために用意した正月飾りを燃やし、来て下さった神様を見送るための行事です。
その煙で厄払いをしたり、餅などを焼いて食べ無病息災を祈願するとも言われています。
また、正月飾りとしてよく見かける物に持ち花というのがあります。
柳の枝に紅白の団子や紙で作った小判などを飾ったものです。
本来のところは、豊作を祈願して小正月に飾るものなのです。
地域の神社でも、小正月にはどんど焼き以外にもさまざまな行事を執り行うところがあります。
よく聞かれるのは、その年の豊凶や天変地異についてを占う、粥占神事・筒粥神事です。
小正月には何を食べるの?
お正月には、御節や御雑煮を食べますね。
では小正月はというと、有名なところでは小豆粥です。
この風習は中国から入ったもので、家族の無病息災を祈願して15日の朝に食べると良いとされています。
なぜ小豆なのかというと、小豆の赤い色にその理由があります。
昔は赤は、生命を象徴する色であり、邪気を払う色とされていました。
それを体内に取り入れれば、一年健康に過ごせると考えられていたのですね。
さいごに
小正月なんて、旧暦の正月ってだけの話でしょ?昔の名残でしょ?と言った声もあるのですが、確かに「それだけの話」なのかもしれませんが、知ってみると奥深い習わしではないかと感じますね。
それを伝えていくかどうかは、個々の考えもあるし地域性もあります。
でも、たかがと思わずに、一年の始まりの月の行事をするのも良いのかもしれませんね。