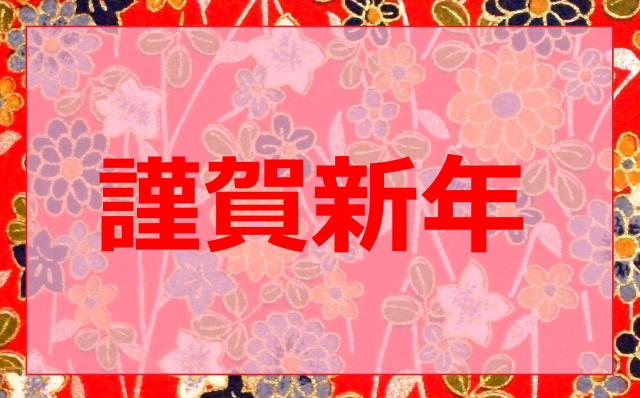おせち料理の由来を知ってますか?食べる意味や歴史を解説

お正月には、いつもと違うご馳走が用意されますよね。
中でもおせち料理は、御重箱に入れられてめでたさが感じられる、お正月ならではの食べ物です。
でもそのおせち料理のこと、詳しく知らない人も多いのでは?そこで、おせち料理についてをまとめてみましたのでご紹介します。
[ad-kiji-1]
おせち料理の由来と歴史
おせち料理の歴史をたどると、平安時代にまでさかのぼります。
昔の日本では、中国の暦で定められた節日(せちにち)に倣い、季節の変わり目で神に供物を供え宴を執り行う御節供(おせちく)という行事をしていました。
節日は元日の1月1日と、五節句の1月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日のことです。
始まりこそ平安宮中の行事でしたが、江戸時代には庶民の間でもその習わしが広がり、特に年の始まりである1月1日に振舞われるお祝い膳をおせち料理と呼ぶようになりました。
やがて、めでたいことを重ねる意味合いから、おせち料理は膳から重箱に変わります。
基本的に四段のお重に料理を詰めるのですが、詰め方は地域による違いがあります。
呼び方はどこも一緒のようで、上から一の重・二の重・三の重・与の重となります。
与の重の与は四のことですが、四は死を連想させることから、縁起を考えて与を使います。
おせち料理の意味は?
お正月に食べるおせち料理は、新しい年を迎えるためにやってくる神様に、豊作などを祈願する意味合いで大晦日に用意される供物です。
そして新年を迎えて、神様からその供物をいただき、家族の健康を祈願しながら揃って食べる物です。
また、神様がおられる三が日中は、炊事などの家事をしない習わしもあり、その間に食べる物として日持ちする料理が用意されているところもあります。
ただ、大晦日からおせち料理を食べる地域もありますし、御重に詰める食べ物もまた地域性があるようです。
お重自体も、四段だけではなく五段のところもあります。
それぞれの食材に意味がある?
何度も言いますが、地域でおせち料理として用意される食べ物の違いがありますが、伝統的に取り入れられている食べ物も多くあります。
それらには、願いが込められています。
いくつか紹介しましょう。
・黒まめ
黒は邪気を払う意味と、日に焼けてまめまめしく働けるようにという意味があります。
また、まめに暮らすというのもあります。
・昆布巻き
よろこびが重ねてあるようにという意味と、「子生婦」と当て字で子孫繁栄の意味合いもあります。
・海老
腰が曲がっていることから、長生きをしましょうという意味があります。
・栗きんとん
栗金団と書くので、金運や繁盛を願う意味合いがあります。
・紅白かまぼこ
紅白は縁起の良い色ということと、昔はなかなか魚を食べられない地域でも、白身魚を使った日持ちの良い食べ物として、とても人気がある縁起物として詰められました。
・ブリの焼き物
出世魚であるブリということで、出世の祈願として。
・鯛の焼き物
鯛は「めでたい」という意味合いをかけて、お祝いの象徴で。
さいごに
昔は12月29日、30日頃に、おせちのための料理を忙しなく作るのがよくある風景ではありましたが、最近はデパートで早々に予約販売もされていますし、一人用にコンビニでも売っているのを目にするようになりました。
普段、あまり口にすることのない料理も詰められていますが、今風にアレンジされている物も多くあります。
いずれにせよ、日本らしい風習ですから、その意味合いなどは大事にしたいですね。