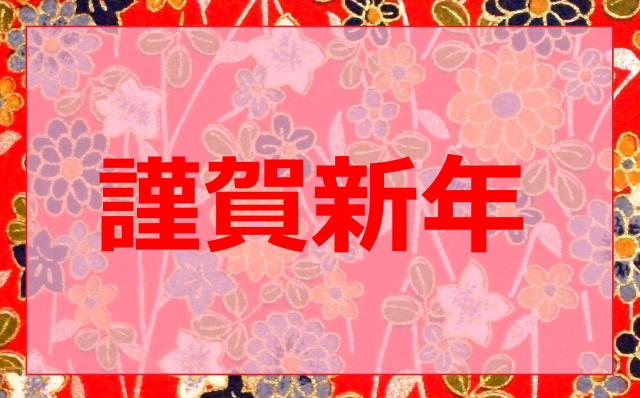七草粥の由来と意味を教えて!七草の種類ってなんだっけ?

お正月になると、独特の行事がありますよね。
その1つが七草粥ですけれど、詳しく分かる人はあまりいないかもしれません。
そこで、七草粥のよくある疑問点から、基礎知識的なものを3つ紹介します。
ぜひ参考にして七草粥を楽しんでくださいね。
[ad-kiji-1]
七草粥の由来は?
七草粥の元は、昔の中国の風習からきています。
中国では、1月1日から8日までを新年の運勢を占う日として、順に鶏・犬・猪・羊・牛・馬・人・穀を占う対象としていました。
人は1月7日で、この日は暦法で決められた1年に5回ある節句に当たります。
5回ある節句・五節句には、邪気を払い生命力をいただく意味合いで、その季節の植物を食べる(飲む)と決まっています。
1月7日は七種類の草で、これを6日までに集めて7日の朝に煮て食べていたそうです。
この風習が、平安時代の日本に伝わります。
その頃の日本には、新年に若草を摘み新しい生命力をいただく風習がありました。
この2つの風習が結びつき七草粥となりました。
江戸時代には、五節句が庶民に広まり、1月7日には七草粥を食べて無病息災を祈願するようになったのだそうです。
七草粥を食べる理由は?
七草粥を食べる理由としては、由来にあるように五節句ごとに定められた季節の植物から強い生命力をいただき邪気を払うことです。
このような神秘めいた理由は、現代では弱い気もしますね。
ところが、七草粥で使われる七草は、理にかなった効果があるのです。
そのことから、お正月のご馳走やお酒で疲れた胃腸を整えるため、七草粥を食べるのが現代での理由と言えます。
七草の種類と、その意味は?
七草粥を食べるのは、七草の生命力をいただく意味合いがあり、それが理にかなっているということを七草を紹介しながら解説します。
・芹(せり)
日本のどこででも自生している植物です。
水田や川など、水分の多めの土壌を好みます。
日本では古くから薬草として食べられ、食欲増進・解熱・神経痛などの効能があります。
また競り勝つという語呂合わせで、1年の始まりに食べると良いとも言われます。
・なずな
別名ぺんぺん草で知られている、多くの人に馴染みのある植物です。
止血・抗炎症・鎮痛・利尿・解熱などに効果があります。
利尿作用があることで、むくみにも効果があります。
汚れを払う草ともされています。
・御形(ごぎょう)
主に喉に関係する病に良いとされていて、咳や痰を抑えたり喉の痛みを取り除く効果があります。
母子草(ははこぐさ)とも呼ばれ、これで人の形を作り3月3日に母と子で川に流すことで、厄災を払うのに使われたと言います。
・はこべら
人の生活するそばで自生し、春から夏にかけてはびこることから、繁栄祈願として食べられます。
カルシウムや鉄分を多く含み、腹痛や消炎効果があります。
また、母乳の出を良くする効果もあります。
・ほとけのざ
良く知られているピンクの花のほとけのざのことではなく、コオニタビラコという植物が七草粥では使われます。
胃の状態を整え、食欲を増進させる効果があります。
歯痛にも効果があります。
仏様の安座という意味合いがあります。
・菘(すずな)
野菜のカブのことで、七草粥には葉が使われます。
食物繊維を多く含むので、消化を助け便秘に効果があります。
体内の不要な物を排出する効果があることから、肌トラブルの解消に有効です。
神様を呼ぶ鈴という意味合いもあるので、縁起の良い野菜でもあります。
・清白(すずしろ)
野菜の大根のことで、七草粥には葉が使われます。
咳や痰を抑え、消化を助ける効果があります。
二日酔いにも良いとされています。
汚れのない清白という意味合いがあります。
さいごに
七草粥に使われる七草は、春の七草と呼ばれています。
対して、秋の七草もあるのですが、こちらは食べるのではなく愛でる七草と言った方が良いでしょうか。
万葉集に登場する二首が元であると言われています。
では秋の七草とは。
萩(はぎ)・桔梗(ききょう)・葛(くず)・女郎花(おみなえし)・藤袴(ふじばかま)・尾花(おばな)・撫子(なでしこ)となります。
春の七草と合わせて覚えたいですね。