亀崎潮干祭2018年の日程は?見どころやアクセス情報も

Photo: 亀崎潮干祭 by Osamu Goto
愛知県愛知県半田市亀崎町では、毎年5月に亀崎潮干祭があります。
このお祭りは、地元の神前(かみさき)神社の祭礼として執り行われています。
独特の知多型(半田型)と呼ばれる山車の行事が、見どころの1つである亀崎潮干祭について、日程やアクセスの方法などを調べてみましたので紹介します。
[ad-kiji-1]
亀崎潮干祭2018年の日程
亀崎潮干祭は、毎年5月3日、4日に執り行われています。
2018年も変更などはなく、通常通りの日程となります。
ちょうどGW中のお祭りですから、どこかに出掛けたいと考え中でしたら、観光を兼ねてのお出掛け先におすすめですよ。
神前(かみさき)神社の祭礼行事としては、実は4月10日からいわば準備が始まっています。
詳細については、下記の通りです。
| 4月10日 | ごま掘り 新居運河 |
|---|---|
| 4月17日 | 山車組み上げ ※予備日24日 |
| 4月25日~5月1日 | 囃子稽古 組事務所、車元宅ほか |
| 5月 2日 | 役割 ※着帳は20時 |
| 5月 3日 | 潮干祭(前の日) ※雨天順延 |
| 5月 4日 | 潮干祭(後の日) ※雨天順延) |
| 5月 5日 | 山車下ろし、新車元打込 ※祭典が順延した場合は8日 |
[ad-kiji-2]
亀崎潮干祭とは?
亀崎潮干祭の起源となったものは、定かではありません。
言い伝えとしては、室町時代の応仁・文明時代のころに、亀崎に移住した武家10数軒の発案で始まったという説があります。

Photo: 亀崎潮干祭 by Osamu Goto
伝承によると、荷車のような山車に笹竹を四方に立て、神紋の染抜幕を笹竹に張って囃子を入れ、町内の曳き廻しが行われたとされているのだそうです。
歴史資料などを遡って調べたところ、元禄から宝暦時代の頃まで確認することができているとのことで、少なくとも300年以上は続く歴史あるお祭りであることが分かっています。
山車は、幾度か新しくしたり改良がされたりしましたが、18世紀中には現在の形態である知多型(半田型)になっていたようです。
その歴史的価値が認められ、1980年には愛知県の有形民俗文化財として、2006年には「亀崎潮干祭の山車行事」が国の重要無形民俗文化財に指定されました。
さらに2016年、「山・鉾・屋台行事」の1つとして、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。
ユネスコの方は、2016年の12月に登録されたばかりですから、それから初めての亀崎潮干祭となりますね。
[ad-kiji-3]
亀崎潮干祭のアクセス情報
亀崎潮干祭は、神前神社・海浜緑地(山車の海浜への曳き下ろし時の観覧場所)・尾張三社(御旅所)の三カ所が会場となります。
車でのアクセス
・知多半島道路 阿久比IC下車-衣浦大橋方面 約15分
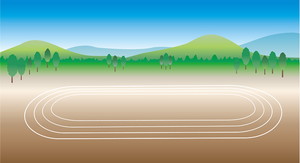
駐車場ですが、無料臨時のものが用意されるのですが、グランドを使用するために雨天ですと場合によっては閉鎖となりますので注意して下さい。
場所については、下記サイトページにて確認をしてください。
注意事項などのチェックもしておいた方が良いかと思います。
参考:亀崎潮干祭 臨時駐車場
公共交通でのアクセス
・JR武豊線 亀崎駅下車 神前神社まで徒歩約15分
・名鉄河和線 知多半田駅下車-知多バス乗車-県社前下車 約25分
[ad-kiji-4]
亀崎潮干祭の見どころ
見どころとなるのは、山車の海浜への曳き下ろし行事です。

これは、神前神社祭神・神武天皇が、海より彼の地に上陸されたという伝承が祭りの由来となっていて、干潮の浜へ5輌の山車を曳き下ろして、からくり人形技芸の奉納などが行われます。
つまり亀崎潮干祭で登場する山車は、からくり人形が乗せられた型となっていて、高さも5~7mほどになる大きな物なわけです。
その山車が5輌、浜辺に揃う姿は勇壮で、見応えがあります。
また、装飾や彫刻が見事なものなので、間近で見られる機会があったら必見です。
名工の技術を目にする機会は、逃してはいけないように思えます。
それぞれの山車に乗せられているからくり人形は、もちろん違うものとなっていて、演目も違いますから、1つ1つ見ておきたいですね。
さいごに
山車に関しては、「半田山車祭り保存会」というサイトの中で紹介されているものが分かりやすく、またそれぞれの法被についても案内されています。
行く前にチェックしておくと、よりお祭りを楽しめるのではと思います。









