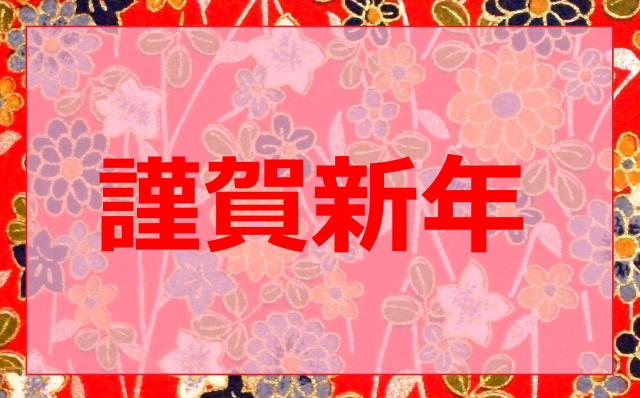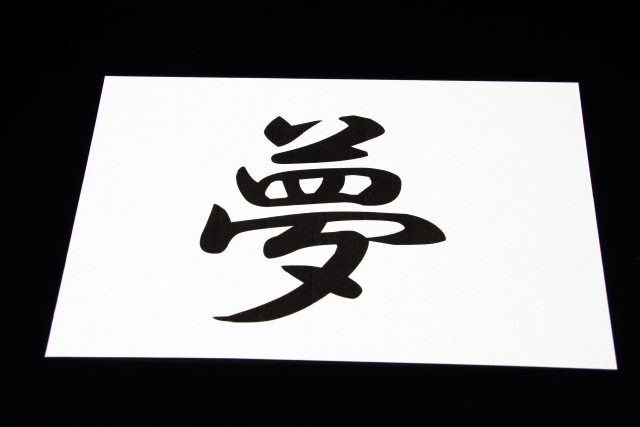正月飾りはいつからいつまで飾るの?正しい飾り方・捨て方

昔は年末になると、どこの家の玄関先や車のフロント部に飾られていた正月飾り。
今でも、田舎の地方だったり、トラックなどには正月飾りが飾られています。
マンションなどではめっきり見なくなりましたが、日本の正月の風習、未来へ受け継いでいきたいところです。
正直、正月らしいものだし、是非今回から自分の家でもやってみたいけど、いつからつけるとか、いつまでつけるとか、更にはどうやって処分するとか、分からないことだらけで諦めている人も多いのではないでしょうか。
そこで、ここでは正月飾りについてまとめてみました。
[ad-kiji-1]
正月飾りはいつからつけるの?
まず、正月飾りはいつからつけるものなのでしょうか?
自らつけていない人は、気づいたらいつの間にか玄関や車についているイメージではないですか?
実は飾り初めは決められており、正月飾りは、12月25~28日の間に飾ると良いと言われています。
師走と言われる1年で最も忙しい時なので、いつの間にか状態になっているのでしょう。
ちょうど、クリスマスも終わり、気づいたら年賀状や正月の準備で追われているとき、ついつい忘れがちになってしまいますが、忘れずに飾るようにしましょう。
また、万一忘れてしまったときや、旅行などにいっていて無理な場合は、ズバリ12月30日が良いです。
むしろ12月29日、31日は避けた方が良いのです。
というのも、29日は「苦が待つ(末)」とされ、縁起が悪いとされており、また31日はその年の飾る日が1日のみで「一夜飾り」となり、神様に失礼とされているので、消去法で30日と言うわけです。
正月の飾りはいつまで飾るの?
今度はいつまで飾るかと言う問題です。
サラリーマンなどだと、学生時代が嘘のようにカレンダー通りに出勤で、正月ボケに浸る前に日常が戻ったりするので、これまた忘れがちです。
しかし、これに関しては、実は地域差がありまちまちだったりするのです。
具体的には関東地方では1月7日まで、関西地方では1月15日までなんて言われていますが、地域によってまちまちなのが実情。
つまり、明確なこの日という全国共通の決められた日がないのです。
その町の地主さんのような昔からあるご家庭の状況を見るなり、話を伺ったりして、自分の住んでいる町の風習を知るのも良いでしょうね。
飾る時とはずす時・捨てる際の注意点
最後に、お正月が終わり、正月飾りをはずす時、捨てるときの注意点です。
これに関しても、前述したように地域差があり、関東地方など一般的には、は1月7日にはずして、1月11日に処分します。
関西地方では、1月15日にはずして、その日じゅうに処分する形です。
処分方法は、大きく分けて2通りあり、神社で捨てる場合と自分で捨てる場合です。
まず、多くの神社では、1月15日に「どんど焼き」と言われるものが行われ、正月飾りを焼却が可能です。
関東などでも15日が多いみたいなので、その場合は11日にはずして、数日間は保管しておく形ですね。
基本的には、どんど焼きの際に、お塩で清めて焚き上げてくれるので、やはり神様が宿ると言われている正月飾りなだけに、この方法がベストでしょう。
また、やり方は神社により若干異なる場合もあるようなので、行く予定の神社のサイトなどを事前に確認してみるのも良いと思います。
また、どうしてももう仕事は始まっているし、神社には行けないと言う場合もあると思います。
そんな場合が、自分で捨てる方法です。
当然ながらポイ捨てなどせず、しっかり細分して、塩で清め、丁寧に新聞紙に包み、ゴミに出すようにしましょう。
同じにしてしまっては神様に失礼かもしれませんが、大切にしていたぬいぐるみを処分するのと同じようなやり方です。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
「一年の計は元旦にあり」なんて言われているように、 その年最後の行事で、最初の行事ともなる正月飾り。
新年早々、神様を大事にして綺麗に大切に飾れば、きっとその年は良いことがありますよ。