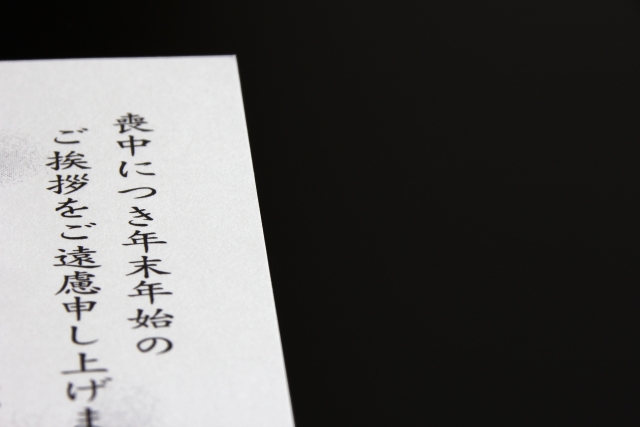正月飾りを外す時期は?いつまでに外せばいいの?

平成の時代になり、例えば祝日に日本国旗を掲げるおうちが少なくなるなど日本の風習が失われつつありますが、お正月くらいはしっかり日本伝統の風習を守っていきたいものです。
そこで、お正月に玄関や車に飾る正月飾りについてまとめてみました。
[ad-kiji-1]
正月飾りを外す時期は?地域によって異なる?
昔からの伝統にうるさい昔ながらの地域に住んでいる場合はともかく、都市型マンション住まいなどだと近所付き合いも少ないので、そこまで気にすることもない正月飾りを外すタイミングですが、しっかり知っておかないと、会社で正月飾りを時期を見て外すように言われ、それから慌てて調べるのも年始そうそう慌ただしくなってしまいます。
しっかりと、風習を学んでおきましょう。
まず正月飾りとは総称で、種類により門松、しめ飾りと言われるものですね。
この門松にヒントがあるのですが、門の松という言葉からも分かるように、正月飾りを飾っておく機関を「松の内」と言われています。
その松の内とされているのが、1月7日までなので、つまり正月飾りは1月7日までというのが一般的となっています。
1月7日と言えば、もう一つお正月の伝統行事がありますよね。
そう!七草粥です。
早春に芽吹く七草(セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ)を食べることで、邪気を払い無病息災を祈るものですが、この七草粥を朝頂いて、その後に正月飾りを外すと言うのが定番のようです。
また、最近ではなかなか朝から七草粥を食べられなかったり、会社で正月飾りを外す時などは七草粥を食べない場合も増えていますよね。
この場合は、7日は終わる時、つまり会社だったら7日の業務終了時に外すのがベストのタイミングのようです。
せっかく日本伝統の行事を大事にと、正月飾りをしっかり飾っていても、外し忘れてしまい、逆に失笑されることが無いように気を付けましょう。
クリスマスのイルミネーションやデコレーションを年をまたいでもずっと飾っていると笑われてしまいますよね。
正月飾りでも同様ですよ。
また、1月7日というのは、あくまでも一般的で、地域によっては鏡開きの御餅と同じ、1月11日というところや、1月15日なんてところもあるようです。
しっかりと風習を守っていきたい場合は、古くからもお宅や、近くの神社に聞いてみるのもよいかもしれませんね。
外した正月飾りはそのままゴミで捨てていいの?
では、1月7日なり11日なり15日なりに外した正月飾りは、そのまま燃えるゴミで捨ててしまってよいのでしょうか?なんとなくイメージ的に縁起物なのでNGな気がしますよね。
できれば行いたいのが、神社への持ち込みです。
日付は神社により異なるので、各神社に問い合わせるしかないのですが、基本は1月15日に「どんど焼き」と言う、正月飾りを償却してくれる日があります。
また、その日が予定が合って無理な場合などは、事前に神社で預かってくれるところも多いようなので、一度聞いてみるのが手でしょう。
また、自宅のものならともなく会社の正月飾りで持ち帰れるほど小さなものではない場合など神社まで行けない場合もあると思います。
その場合は、他の燃えるごみと一緒に出すのではなく、お塩で正月飾りを清めて、他とは別の袋でゴミに出すようにしましょう。
面倒くさいなんて思う人もいるかもしれませんが、これで1年の厄が払い落されるのであれば簡単なものですよね。
来年もまた使ってもいいの?
今のエコの観点からすると、たったの1年で、神社で焼却したり、ゴミに出したりせずに、来年も使い続けたいなんて考える人も多いのではないでしょうか。
果たして、来年もそのまま使っても良いのでしょうか。
正月飾りの縁起物としては、1年間の無病息災を祈願するわけなので、1年で使い捨てになり、翌年には効果・効能が無い気がするので、1年ごとに買い替えするのがベストです。
あとは、正月飾りの縁起物とするか、単にお正月のインテリアと考えるかの考え方によって変わってきます。
インテリアとしてのみ考えるのであれば、防腐剤をしっかり入れて、来年も再び飾っても、今の時代らしいかもしれませんね。